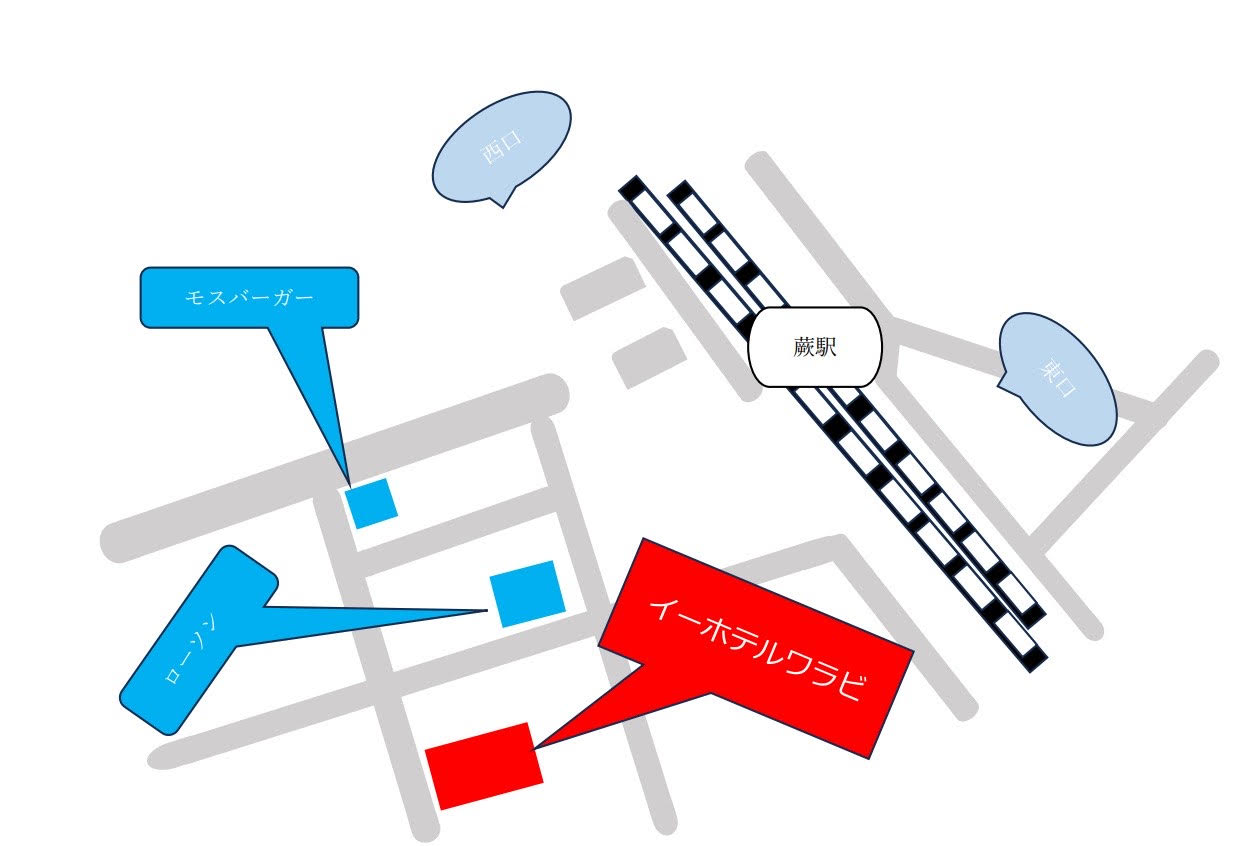ご案内 |
プラン |
飲食店 |
観光 |
イベント |
イーホテルワラビのブログをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
当ホテルは JR蕨駅から徒歩2分 のビジネスホテルとして、
出張やイベント、観光など さまざまなシーン でご利用いただいております。
「蕨・エリアでビジネスホテルを探している」という方は、
ぜひご参考までにチェックしてみてください。
イーホテルワラビのブログをご覧頂きまして、ありがとうございます。
本日は蕨の歴史についてご紹介させていただきます。
埼玉県蕨市は日本で最も面積の小さい市でありながら、
その歴史は驚くほど深い物が有ります。
遡れば、弥生時代の遺跡が発見され、
この地に人々が暮らしていたことが分かっています。
奈良・平安時代には武蔵国の一部として発展し、
中世には戦国武将たちの争いの舞台にもなりました。
江戸時代には中山道の宿泊場「蕨宿」として栄え、
多くの旅人が行き交う街へ。
明治以降は近代化の波を受け、
現在は首都圏として発展を続けています。
本記事では、そんな蕨の歴を弥生時代から現代まで紐解き。
町の変化や文化の魅力に迫ります。
![]()
◆ 弥生時代 ◆
■ (300~500年) 蕨に人が住み始める(金山遺跡)
◆ 平安時代 ◆
■ 998年 寺伝によれば、三学院が創建したという
◆ 室町時代 ◆
■ 1352年 文献上、初めて「わらび」が見られる
(「賀上家文書」に「蕨郷上下」と記載される)
■ 1457年 渋川義鏡(よしかね)が関東探題に任命され、蕨城主になる。
■ 1524年 蕨城が落城する(1526年ともいわれている)
■ 1567年 蕨城主の渋川氏が上総国(千葉県)三舟山で戦死
■ 1591年 徳川家康が三学院に寺領20石を寄進
◆ 江戸時代 ◆
■ 1612年 蕨に宿場が作られたという
■ 1694年 三学院にある子育地蔵がつくられる
■ 1725年 蕨宿が火事となる
■ 1826年 塚越村の高橋新五郎が織物業を始めたという
■ 1861年 皇女和宮が蕨宿の本陣で休憩する
◆ 明治時代 ◆
■ 1870年 石川直中が蕨宿に郷学校を開校する
■ 1872年 新学校制度が始まり、
「蕨郷学校」が「第二十九番小学校」となる(今の北小学校)
■ 1878年 塚越村に「第四十三番小学校」ができる(今の東小学校)
■ 1889年 蕨宿と塚越村が合併して蕨町となる
■ 1893年 蕨駅ができる
■ 1910年 蕨町が台風により大水害にあう
■ 1911年 蕨町の18社の神社を合祀して和楽備神社となる。
また、蕨町に電灯がつき、電話がひかれる
◆ 大正時代 ◆
■ 1915年 「ワラビ」を図案化した紋章が画家の間宮孝太郎によって考案。
■ 1923年 関東大震災がおこる
◆ 昭和時代 ◆
■ 1932年 赤羽から大宮まで電車が走る
■ 1945年 蕨町が3回空襲され、50人が亡くなる
■ 1946年 第1回「成年式」が行われる
■ 1951年 第1回「機まつり」開催
■ 1959年 蕨町が蕨市となる
■ 1984年 第1回「宿場まつり」開催
◆ 平成時代 ◆
■ 1989年 蕨のマスコットキャラクター(市制30周年記念)「ワラビー」くん登場
2010年 蕨のマスコットキャラクター(市制50周年記念)
「Angel WaraBU-!!」(エンジェルわらぶー)登場。
また、蕨市の頭文字「わ」をモチーフとしたシンボルマークが決定
![]()
蕨は弥生時代から現代まで、
長い歴史の中で宿泊場として発展し、
多くの人々が行き交う街でした。
現在もその名残を感じられる場所が点在し、
歴史好きにはたまらない魅力が有ります。
そんな蕨を訪れる際には、
アクセス良好で駅近の蕨のビジネスホテルが便利です。
出張での滞在にも最適で無料朝食付きのプランがあるホテルなら、
朝からしっかりエネルギーチャージも可能。
歴史散策やビジネス利用にぴったりの蕨で、
快適な滞在を楽しんてみてはいかがでしょうか。
蕨の歴史を垣間見る事で
蕨がちょっと好きになったのではないでしょうか。
出張中や旅行でお越しの際
お時間をみつけて、駅前からバスに乗って
人気のスポットでもある三学院や和楽備神社などを訪れ
息抜きに歴史に触れてみるのもおすすめです。
#蕨ビジネスホテル
#徒歩二分
#格安
#朝食付き
#レイトチェックアウト
#蕨イベント
#たまアリ
#駅近
#アクセス良好
#便利
#リーズナブル
#お得
#人気
#ランキング
#おすすめ
#口コミ高評価